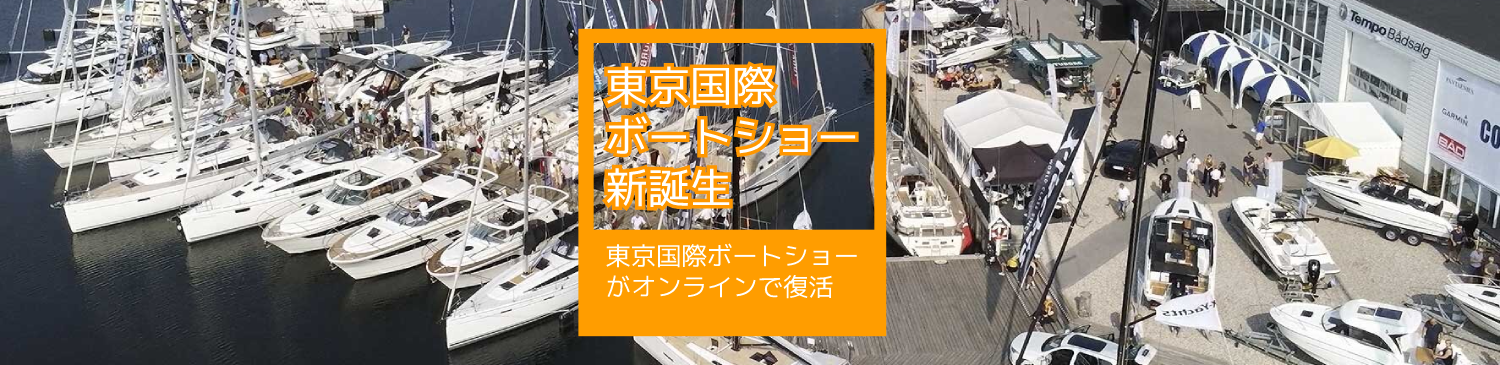※スマホの方は、横向きでご覧下さい。
伊豆の旅
「今年は、伊豆へ行くぞ!」
お父さんは、リビングルームにいる家族皆に言った。
「伊豆?」
「そうだ。伊豆だ。下田の辺りから少しずつ北東へ移動していこうと思う」
お父さんは、お母さんに説明した。今年の夏休みのヨットでのクルージングの計画だった。去年は、千葉の房総半島を旅したが、今年は伊豆半島を巡ろうというつもりらしかった。
「またヨットで行くの?」
ゆみは、お父さんに聞いた。
「そうだよ。ゆみは、ヨットで行きたくないか?」
「うん。別にヨットでも行ってもいいけど、電車で行く方が良いかな」
ゆみは、正直にお父さんに答えた。
「そうね。お母さんも、伊豆に行くんだったら、女学生の頃に川端康成とか巡ったことあるから、懐かしいし行ってみたいけど、ヨットより電車で行きたいわね」
お母さんも、ゆみに賛成した。
「なんだ、そうか」
伊豆に行きたいというよりも、家族でヨットに乗って出かけたいお父さんは少し寂しそうだった。
「それじゃ、お父さんと私で先にヨットで行っているってことよね」
祥恵は、皆の話をまとめて言った。
「そういうことになるかな」
お父さんが祥恵に言った。結局、ゆみとお母さんが電車で行きたいということで、お父さんと祥恵で先に横浜のヨットクラブからヨットで出航して、下田港に着いていることになった。お母さんとゆみは、後から電車に乗って追いかけて、下田港で落ち合うことになったのだった。
「下田からは、一緒にヨットで移動しような」
お父さんは、お母さんとゆみに話した。
「ブータ先生、今年は伊豆に行くんだって」
ゆみは、夜寝る前にベッドの中でブータ先生と話していた。
「また今年も、おいらも一緒に旅行に行ってもいいのかな?」
「もちろんよ」
「そうか、それは楽しみだな」
ブータ先生が、ゆみに嬉しそうに言った。すると、横で寝ていた猫のまりちゃんと美奈ちゃん、それに犬のメロディも自分たちも行けるのかどうか心配そうに小さく吠えた。
「もちろん、美奈ちゃんも、まりちゃんも、メロディも一緒に行くわよ」
ゆみは、皆に答えた。それから、犬や猫は電車に乗せるの大変だから、明日お父さんにヨットに行くとき、一緒に連れていってもらえるように頼まなきゃと思っていた。
「ね、お母さん。まりちゃんたちも伊豆に一緒に行けるでしょう?」
「そうね。置いていくわけにはいかないものね。電車だと大変だから、お父さんにヨットに一緒に乗せてもらいましょう」
「うん」
ゆみは、大きく頷いた。
「ゆみ。そっちの野菜を切ってくれる?」
「はあい」
ゆみは、包丁で夕食用の野菜を刻み始めた。
「なかなか上手に包丁を使えるようになったではないか」
ブータ先生がキッチン台の上で眺めながら、ゆみに言った。
「それはそうよ。あたし、ちゃんと学校の家庭科の時間に習ったもの」
ゆみは、ブータ先生に返事した。
「ね、ブータ先生も夕食のお手伝いしてよ」
「ああ、もちろん構わんよ」
ブータ先生は、ゆみが刻み終わった野菜をお鍋に投入して、グツグツと煮込んでいた。
「ゆみ殿。塩とか調味料を取ってくれ」
ブータ先生は、お鍋で野菜を煮込みながら、ゆみに言った。ゆみは、側にあった調味料を手に取って、ブータ先生に渡した。
「あら、ゆみは、随分手際よくお料理できるようになったじゃない」
お母さんには、ブータ先生が料理しているところは見えていないので、全部ゆみ1人でお料理していると思っているようだった。
「家庭科で習ったものな」
ブータ先生が、お母さんに答えるが、ブータ先生の声は、お母さんには聞こえていないので、代わりにゆみがお母さんに答える。
「ただいま」
夏のバスケの部活練習から帰ってきた祥恵が台所に入ってくる。
「あ、美味しそう」
祥恵は、台所内に充満している今夜の夕食のにおいを嗅ぎながら言った。
「今夜の夕食は、ほとんど全部ゆみが作ったのよ」
お母さんが、祥恵に言った。
「へえ、美味しそうじゃない。ゆみはお料理上手だね」
祥恵は、お鍋の中の料理を覗きこみながら、ゆみに言った。
「うん。だって家庭科の授業でちゃんと習っているもの」
ゆみは、祥恵にも同じ言葉を繰り返していた。
「祥恵は、家庭科とかの授業はないの?」
お母さんが祥恵に聞いた。
「あるよ。家庭科の授業は、私もけっこう得意なんだよ。どうして中間とか期末試験に家庭科がないのかなっていつも思うの。家庭科の試験だけだったら、絶対に私でももっと点数が良いのに」
祥恵は、お母さんに答えた。
「へえ、そうなの」
お母さんは、祥恵に答えた。
「その割には、あなたはあんまり家ではお料理しないわね」
「それはそうよ。家では、ゆみが全部お母さんとお料理とかしているのに、私がする必要ないでしょう」
祥恵は、答えた。
「ゆみ殿。おいらをテーブルの上に乗せてくれ」
ブータ先生は、ゆみに自分の小さな身体をダイニングテーブルの上に乗せてもらうと、お鍋を片手に、テーブルの上に並べられた食器にそれぞれ、出来上がったお料理を盛りつけていた。ブータ先生が盛りつけた後の食器に、ゆみが付け合わせのポテトを配っていく。
「あら、盛りつけまでやってくれたの」
お母さんは、夕食をお皿に盛りつけているゆみに言った。お母さんには、ブータ先生が盛りつけているところは見えていないようだ。
「ブータ先生、ごめんね」
ゆみは、ブータ先生に言った。
「ブータ先生も手伝ってくれているのに、あたし1人がお手伝いしているみたいに思われていて・・」
「いやいや、おいらは、ゆみ殿のお役に立てれば、それだけで良いんじゃよ。ドラえもんとのび太君のようなものじゃな」
ブータ先生は、ゆみに答えた。
伊豆急につづく
 今井ゆみへのお仕事のお支払いや本サイト上の小説などを読んだ投げ銭にご利用下さい。
今井ゆみへのお仕事のお支払いや本サイト上の小説などを読んだ投げ銭にご利用下さい。