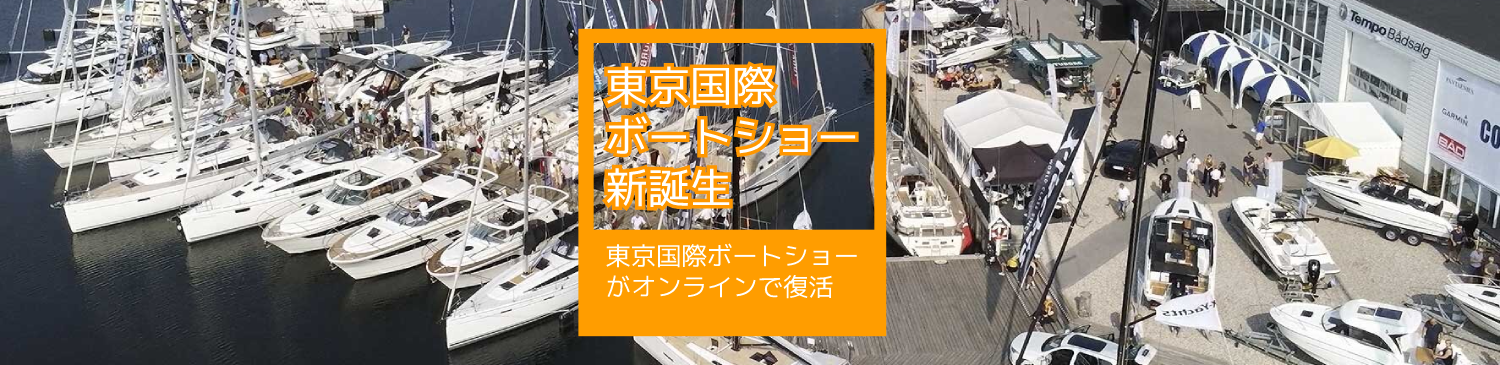※スマホの方は、横向きでご覧下さい。
50 ゴール!
「はい、ゴール!」
祥恵がマラソン大会のゴール地点にあるテープを切ってゴールすると、タイムキーパーが自分の持っているストップウォッチのスイッチを押しながら叫んだ。
祥恵がゴールしたとき、9年生と8年生は何人かゴールしていたが、7年生はまだ誰もゴールしていなかった。
ハアハア・・
祥恵は、走ってきたので、自分の息を整えながら、ゴール地点の草の上に座り込んでいた。さすがに、ペース速かったかな、ちょっと疲れたなと思っていた。
祥恵がゴールしてから、20分ぐらいして佐藤や柳瀬たち7年生の男子がゴール地点に現れた。佐藤たちがゴールラインを切って、ゴールすると、とっくにすっかり息も整え終わってくつろいでいた祥恵が、タオルを掛けてやっていた。
「祥恵、速いじゃん」
「いつゴールしたの?」
佐藤たちは、息を弾ませながら、祥恵に聞いた。
「20分ぐらい前かな」
祥恵は、佐藤たちに答えた。
「速ぇーな」
佐藤たちは、祥恵の速さに驚いていた。それから10分ほどして小倉夕子が7年生の2番目の女子としてゴールした。その後、次々と7年生のランナーたちがゴールラインに入ってきた。
祥恵がゴールしたときは、タイムキーパーはゴールラインでテープを持って迎えてくれたが、今はもうゴールしてくるランナーの数が多すぎるため、いちいちテープを持っていられないので、ゴールのテープは無くなっていた。
一番最後にゴールにやって来たのは、ランナーではないが、運営車のハイエースに乗ったゆみたちだった。各水の配布所を廻って撤収作業してからゴールに来たので、一番遅くなってしまったのだった。
「それでは表彰式をはじめます」
壇の上に立った司会の案内でマラソン大会の上位者たちは、前に出て上位のご褒美をもらっていた。7年生ではトップの祥恵は、
「今井祥恵さん!」
壇上から司会に呼ばれて、前に出ると一番大きなご褒美の箱とトロフィーをもらっていた。トロフィーは、毎年上位クラスの持ち回りで優勝すると、そこに名前入りのテープをぶら下げてもらえるのだった。
「それで、今年度のマラソン大会の総合優勝者は、今井祥恵さん」
祥恵は、再度呼ばれて壇上に立たされていた。
「お姉ちゃん、総合優勝!」
ゆみは、祥恵が壇上に立っている姿を見てつぶやいた。
「総合タイムで計測すると、祥恵が9年生たち上級生よりも一番速かったみたいだな」
大友先生が言った。
「おまえの姉ちゃん、速いな」
ゆみの腕に抱かれているブータ先生が、ゆみに囁いた。
表彰式のあと、ゆみが狭山湖内の公園に仮設された女子更衣室の中に入ると、祥恵がほかの女子たちと一緒にタオルで身体を拭いてから着替えていた。
「ゆみ。ちゃんとマラソンのお手伝いはしたの?」
祥恵が、更衣室に入ってきたゆみに気づいて、聞いた。
「うん。大友先生と一緒に周ったの」
「そう。お姉ちゃん1位だぞ」
祥恵は、ゆみにトロフィーを見せながら笑顔で言った。
「すごいね。これ、おうちに持って帰っていいの?」
ゆみは、祥恵から見せられた大きなトロフィーを抱えながら聞いた。
「これはダメよ。1組の教室に飾るんだってさ」
祥恵は言った。
「その代わり、これはもらえるって。ゆみにあげるよ」
祥恵は、表彰式でもらった大きな箱をゆみに渡しながら言った。
「何が入っているの?」
ゆみは、大きな箱の中をカラカラ揺らしてみながら聞いた。
「さあ、なんだろう?開けてごらん」
祥恵は、ゆみに言った。
「毎年の恒例だと、授業で書くのに使えるノートブックなんだって」
美和が言った。
「ノートブックか。つまんないね」
「勉強に役立つものしかくれるわけないじゃん」
百合子が言った。
「それはそうだよね。じゃ、この箱の中身、ぜんぶゆみにあげるよ」
勉強には、あまり興味の無い祥恵は、答えた。
「ゆみちゃん、良かったね。ぜんぶもらえるって」
「うん。開けてみていい」
「じゃ、一緒に開けよう」
着替え終わった百合子が、ゆみの横にやって来て、一緒に机の上の箱を開けた。
「日記だ!」
ゆみは、箱の中から出てきたものを見て叫んだ。
「なんか便せんとか封筒もいっぱい入っているじゃない。日記帳とかお手紙セットってことかな、今年は」
百合子が言った。
「ますます、私はいらないな。手紙なんて書かないし」
「これは、おまえさんのためのものじゃな」
ブータ先生が、ゆみの方を見て言った。
「あたしのため?なんで?」
「まあ、大事にとっておけ。今にわかるから」
ブータ先生は、いたずらっぽく笑って見せた。ゆみには、その意味がよくわからなかった。よくわからなかったが、毎年の恒例のノートブックでなく、今年は日記帳とかになったのは、またきっとブータ先生の何か差し金なんだろうなってことはわかった。
「ゆみには重すぎるから、お姉ちゃんがおうちまで持っていってあげるよ」
着替え終わった祥恵が箱の中に入っていた日記帳とかをまとめながら言った。
「あれ、お姉ちゃん。またグリーンのスカート履いてる」
ゆみは、着替え終わった祥恵の姿を見て言った。祥恵は、このグリーンのスカートと薄いブルーの膝丈のデニムスカートをいつもよく着ていた。
「だって、着てきたジャージは汗だらけなんだもの。あれ着て、電車で帰れないでしょう」
ゆみは、身体をしゃがませると、祥恵の履いているスカートの中を覗きこんだ。
「何よ」
祥恵は、慌てて自分のスカートを押さえて、ゆみに言った。
「お姉ちゃん、白だった。またパンツもグリーンに合わせているのかと思った」
「そんなわけないでしょう!」
祥恵は、ゆみのことを怒鳴った。
「パンツがグリーンって?」
「え、前に私がこのグリーンのスカート履いているときに、たまたまパンツもグリーンだったものだから、私の下着はスカートに合わせた色しか履かないとおもっているのよ、ゆみったら」
「へえ、そうなんだ」
百合子は、ゆみのことを笑った。
「祥恵が、そんなグリーンのパンツにグリーンのスカートなんて、こだわったおしゃれなんかするわけないじゃん。あるとしたら、パンツだけ履いて、スカートを履かずに学校まで来ちゃうとか・・」
美和が、祥恵に言った。
「なんか腹が立つけど、確かに私ならやりそうで言い返せない」
祥恵は、美和に答えた。
「でもさ、グリーン色のパンツってどんなの?気になるから今度、私にも見せてよ」
百合子が、祥恵に聞いた。
「え、いいから。その話は」
祥恵は、百合子に言われて頬を赤らめた。
「私、知ってるよ。祥恵のグリーン色のパンツって。前に、部活の前に更衣室で着替えていたときに履いてたやつのことでしょう」
美和は、祥恵に言った。祥恵と美和は、同じバスケ部だから、よく更衣室で一緒に着替えることもあったが、帰宅部の百合子は、2人と更衣室で一緒になることは少なかった。
「今度、履いてきたとき見せてね」
「いいけど。たぶん、あれはもう履かないかもしれない。前にゆみにスカートと合わせてるとか言われて以来、あれ履きづらくて・・」
「そうなの?」
「なんせ、この子って、自分は一切スカートを履かないくせに、人が履いているスカートの中は遠慮もせずに、普通に覗きこんでくるからね」
祥恵は苦笑した。
 今井ゆみへのお仕事のお支払いや本サイト上の小説などを読んだ投げ銭にご利用下さい。
今井ゆみへのお仕事のお支払いや本サイト上の小説などを読んだ投げ銭にご利用下さい。