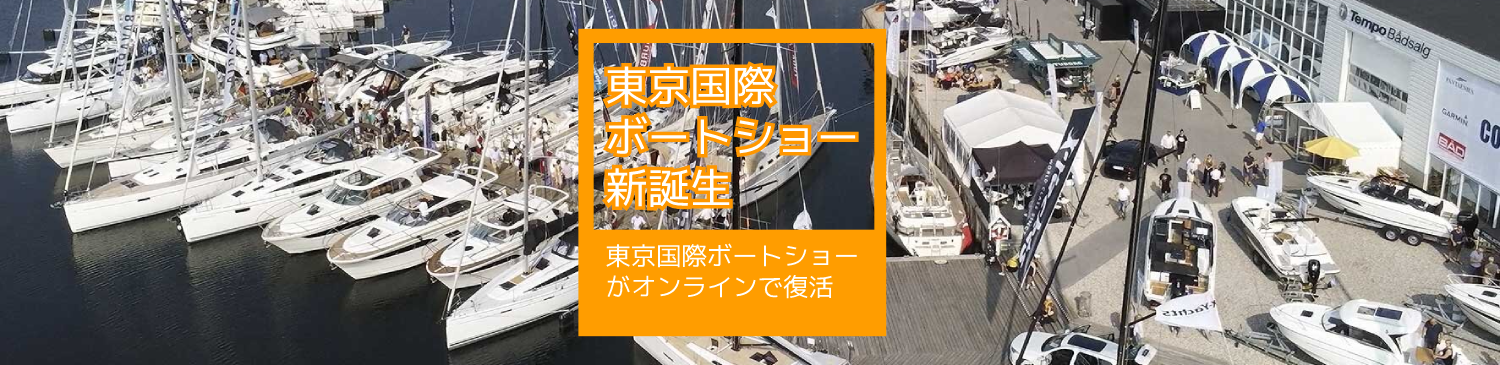※スマホの方は、横向きでご覧下さい。
伊豆稲取
「お父さん、今日はこれからどうするの?」
ゆみは、ヨットの中で朝ごはんを食べ終わったあと、お父さんに聞いた。
「今日は、これから稲取まで行こうと思う」
お父さんは、ゆみに言った。
「稲取?」
「稲取というのは、ここ下田から少し北上したところにある港のことだよ。下田はヨットやらボートがいっぱい停泊していて、黒船の観光客も多く混んでいるけど、稲取は静かできれいな港だぞ。落ち着けると思うよ」
お父さんと祥恵は、朝ごはんを食べ終えると出航の準備をして、ヨットで下田港を出航した。
「ゆみは、まだ眠いならキャビンの中で寝ていてもいいわよ」
「ううん、大丈夫」
ゆみは、お母さんに聞かれて答えた。昨夜は、キャビン右側後部にあるパイプベッドでお母さんと寝たゆみだった。反対側のパイプベッドでは祥恵が寝て、真ん中のキャビンにある長いすのクッションを広げて、そこをベッドにして、お父さんは寝ていた。
「なんか、家族皆で、こういうところでゴロンゴロンして寝ているとホームレスになったみたいだね」
ゆみは、昨夜寝る前に、お父さんに話していた。
「眠くないけど暑い」
ゆみは、お母さんにデッキ上で強い陽差しを受けながらつぶやいていた。ヨットのデッキ上は、夏の強い陽差しでカンカン照りだった。
「本当ね。日傘が必要ね」
お母さんは、持ってきた日傘を差すと、ゆみのことも自分の側に呼んで、ヨットの上で日傘を差しながら腰掛けていた。
「なんだかすごいな。セレブだな」
お父さんは、ヨットのデッキの上で日傘を差しているお母さんとゆみの姿を見ながら話した。
「お母さんの、その白い手袋をして、黒いレースの傘を差しているから、余計にセレブなマダム感がぬぐえないよね」
祥恵も、お母さんの姿をみて言った。お母さんとゆみは、日傘の下にいるが、お父さんと祥恵はカンカン照りのデッキで日の光をたくさん浴びながら、ヨットのセイルワークをしていた。
「祥恵。あなたも日傘かなにかないの?日焼けしてあとが大変よ」
お母さんは、祥恵に言った。
「日傘なんて差していたら、ヨットを走らせられないよ」
祥恵は、ヨットの舵、ティラーを持ちながら、お母さんに言った。お父さんも、ヨットの上の陽差しは、もうすっかり慣れっこになっているようで、真っ黒に日焼けした姿で普通に歩き回っていた。
「あら、向こうからヨットが来るわよ」
お母さんは、日傘を持っていない方の手で、こっちにやって来るヨットを指さした。
「どこ?」
「ほら、あっち」
「あ、本当だ!」
ゆみは、お母さんに教えてもらった方角からやって来るヨットの姿を見つけて叫んだ。
「あ、あっちのヨットいいな。ちゃんと日陰の屋根が付いているよ」
ゆみは、すれ違うヨットを見て叫んだ。向こうからやって来たヨットの、ちょうど操船場所、コクピットにはパイプで組み立てられて、屋根の部分にテントが張られて日陰がちゃんと出来ていた。
「あれはビミニトップっていうのよ」
祥恵は、ゆみに説明した。
「うちのヨットには付いていないの?」
「付いていない・・」
祥恵は、ゆみに答えた。
「あれ、付いていれば暑くないのに」
「でも、あんなの付けていたら、ヨットの操船がしにくくなるでしょう」
祥恵は、ヨットのティラーを握り、操船しながら答えた。
「夏は暑いものだから、日焼けだってして当然よ」
祥恵は、根っからのスポーツマンらしく答えていたが、
「でも、祥恵だって女の子なんだから、肌の日焼けには気をつけた方がいいわよ」
すぐその後に、お母さんに突っ込まれていた。
「ほら、見えてきただろう!」
お父さんは、前方を指さしながら叫んだ。お父さんの指さす前方には、何か突堤が長く伸びていた。
「あれが、どうかしたの?」
普段ヨットに乗らないゆみは、お父さんの指さす意味がよくわからずに言った。
「え、あれが今日の目的地。稲取だよ」
お父さんは、ゆみに説明した。その長く伸びている突堤の先っぽ、奥から一隻のヨットが現れて、こちらに向かってくる。
「なんか、あの先っぽから突然ヨットが出てきたよ」
「本当ね。まるでヨットが出てくる魔法の棒みたいね」
ヨットに乗らないゆみとお母さんは話していた。
「魔法の棒じゃなくて、あの突堤は港の入り口だ。あの中に稲取の港があるんだよ」
お父さんは、ゆみたちに説明した。その稲取の港から出てきたヨットは、ゆみたちの乗るヨットとすれ違って、今ゆみたちのヨットがやって来た方向へと去っていた。
「ね、あのヨットも、ヨットの上のところにテントが付いて、日陰になっていたよ」
ゆみは、すれ違ったとき、向こうのヨットを見て叫んだ。
「ゆみ。あんまり大声で叫ぶと、向こうのヨットにまる聞こえだぞ」
お父さんは、ゆみに注意した。
「普段ヨットに乗らないと、あんまりそう思わないかもしれないけど、こっちのヨットは、向こうのヨットの風上にいるんだからな。向こうのヨットで話す言葉は聞こえてこないかもしれないが、こっちで話す言葉は、全部風上から風下のヨットに向かって流れていくから、向こうには全部聞こえているんだぞ」
「そうなんだ」
ゆみは、お父さんから聞いて驚いていた。
「でも、最近のヨットって確かに、ゆみの言うようにビミニトップの付いているヨットが多いかもね」
「そうだな。まあ、うちのヨットは古いものな」
お父さんは、祥恵に答えた。
「うちのヨットって、そんなに古いの?」
「そうだな。ゆみが生まれるずっと前に新艇で買って乗り続けているからな。もうかれこれ30年ぐらいにはなるかもしれないな」
「え、30年ってすごい!」
「そうね。車だって30年も乗らないものね」
ゆみの言葉に、お母さんも頷いた。
「さあ、入港するぞ!」
お父さんは、30歳のヨットを稲取の港に入港させていた。
稲取アイスにつづく
 今井ゆみへのお仕事のお支払いや本サイト上の小説などを読んだ投げ銭にご利用下さい。
今井ゆみへのお仕事のお支払いや本サイト上の小説などを読んだ投げ銭にご利用下さい。